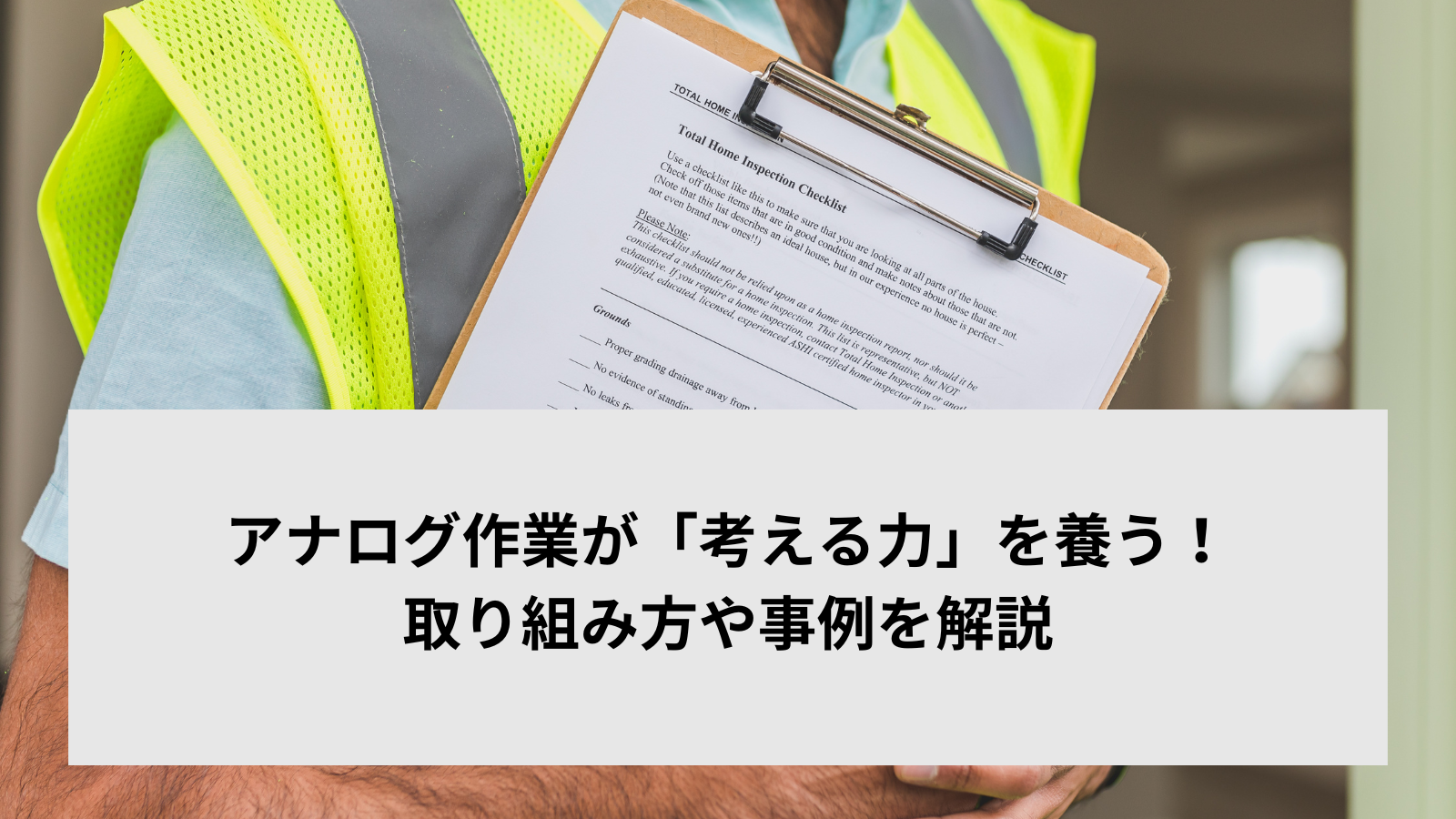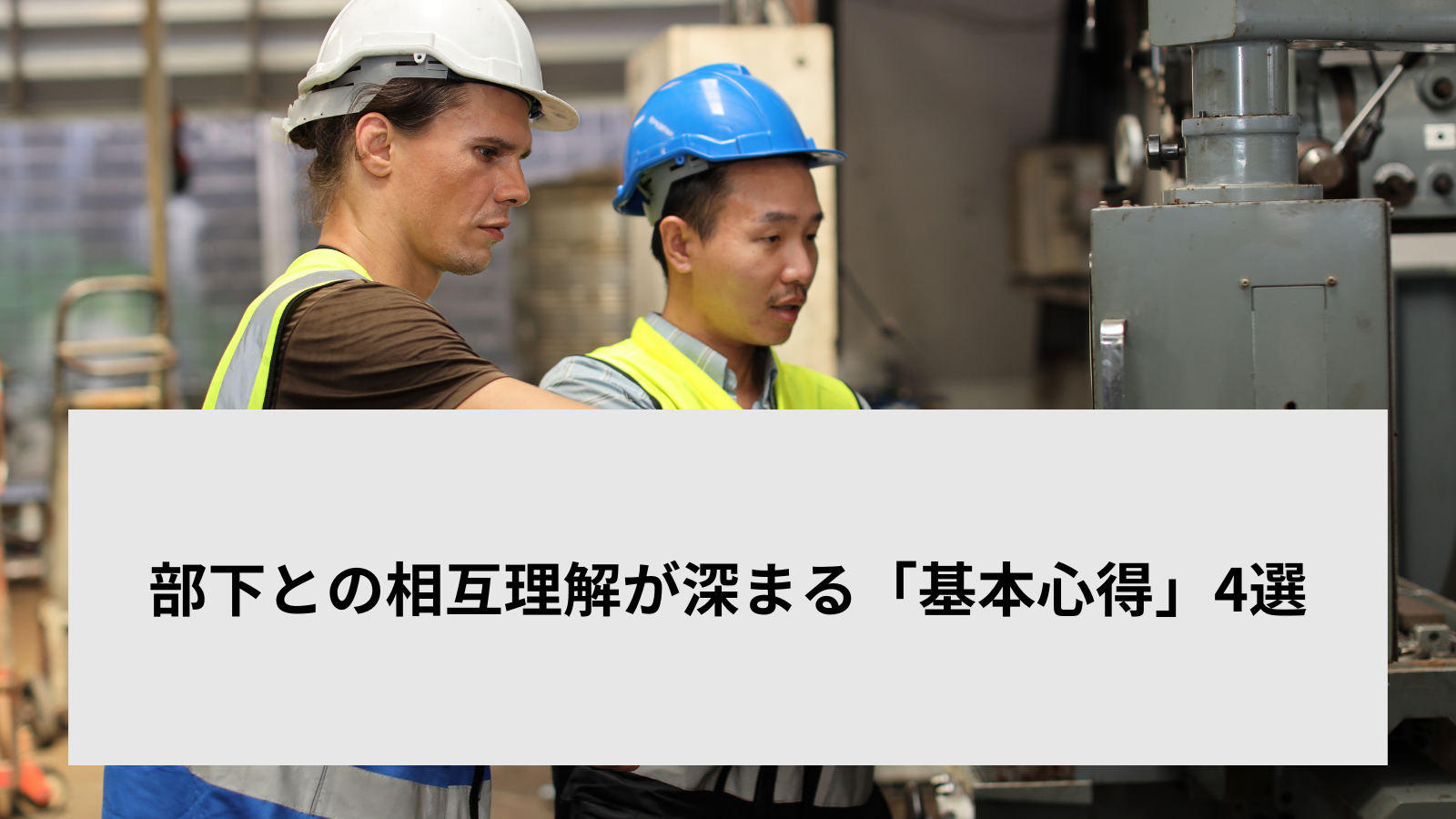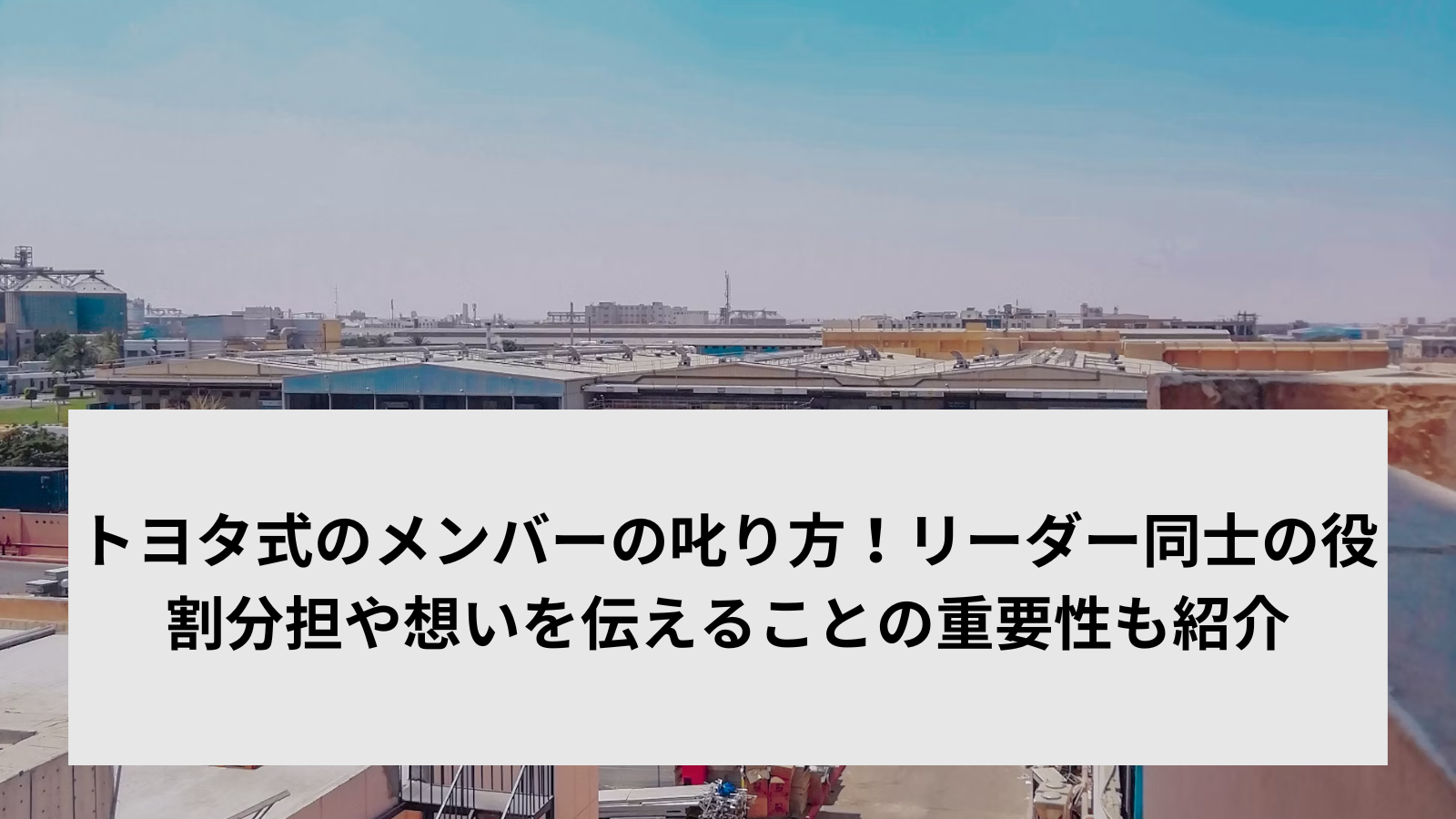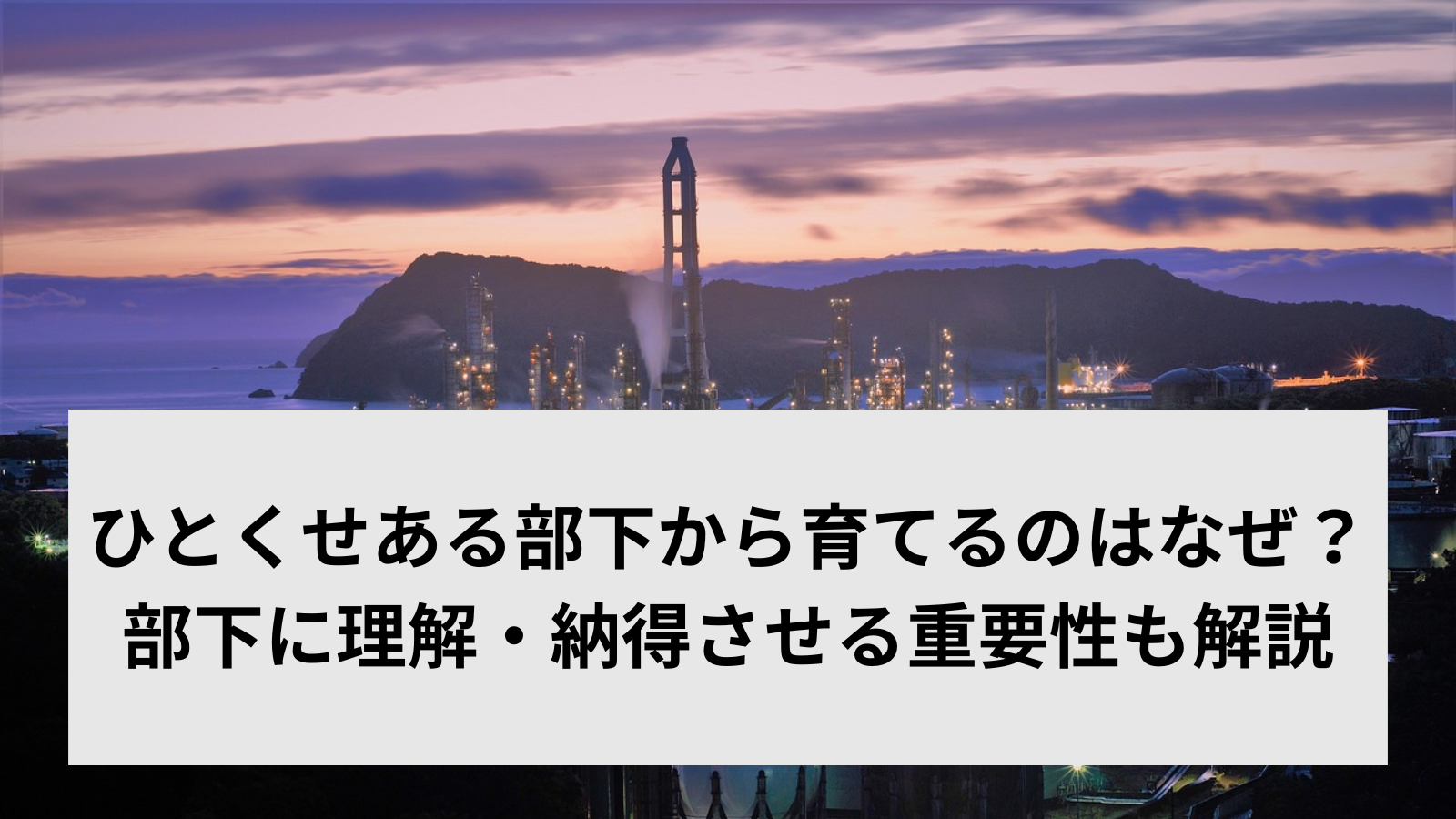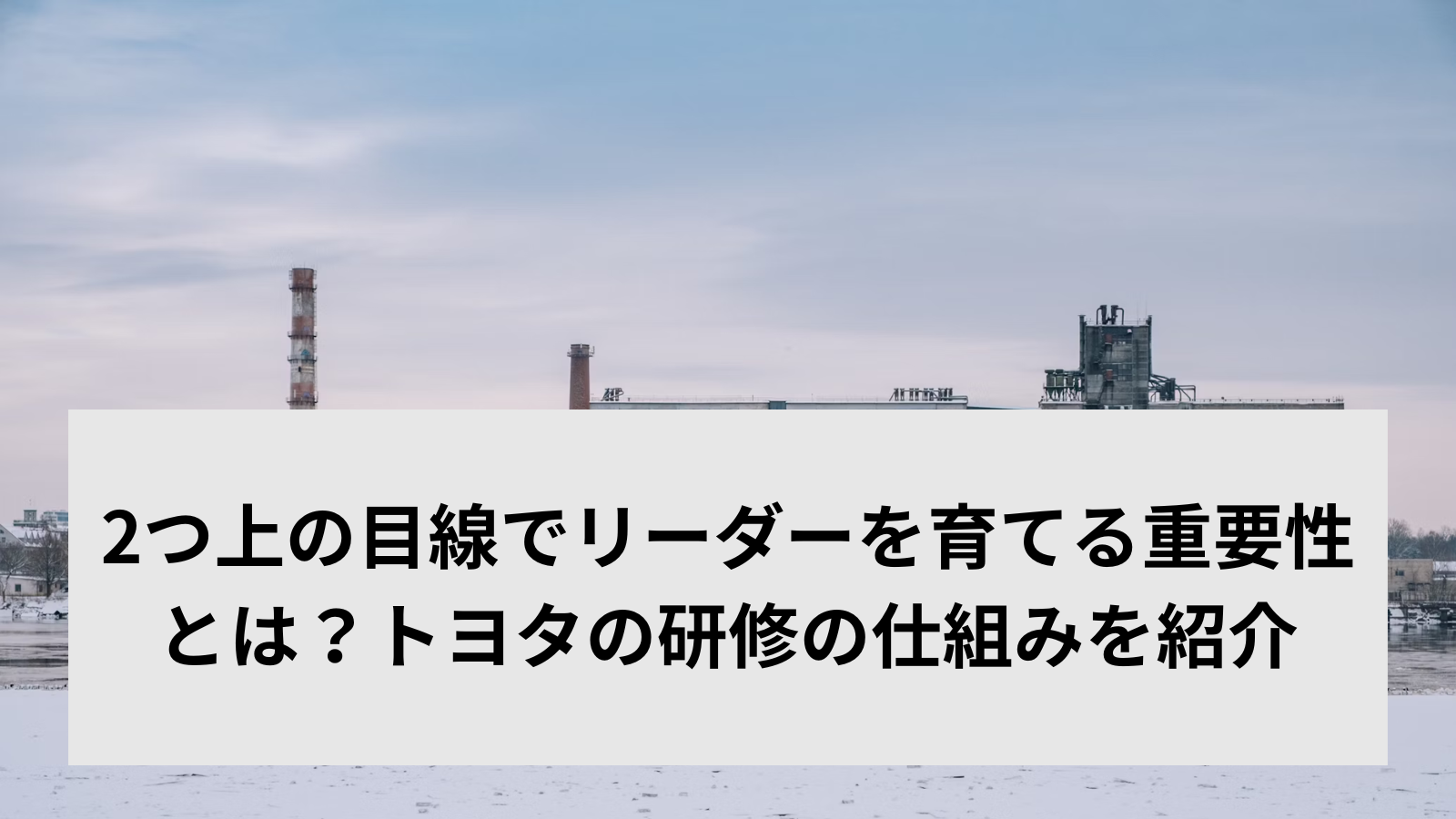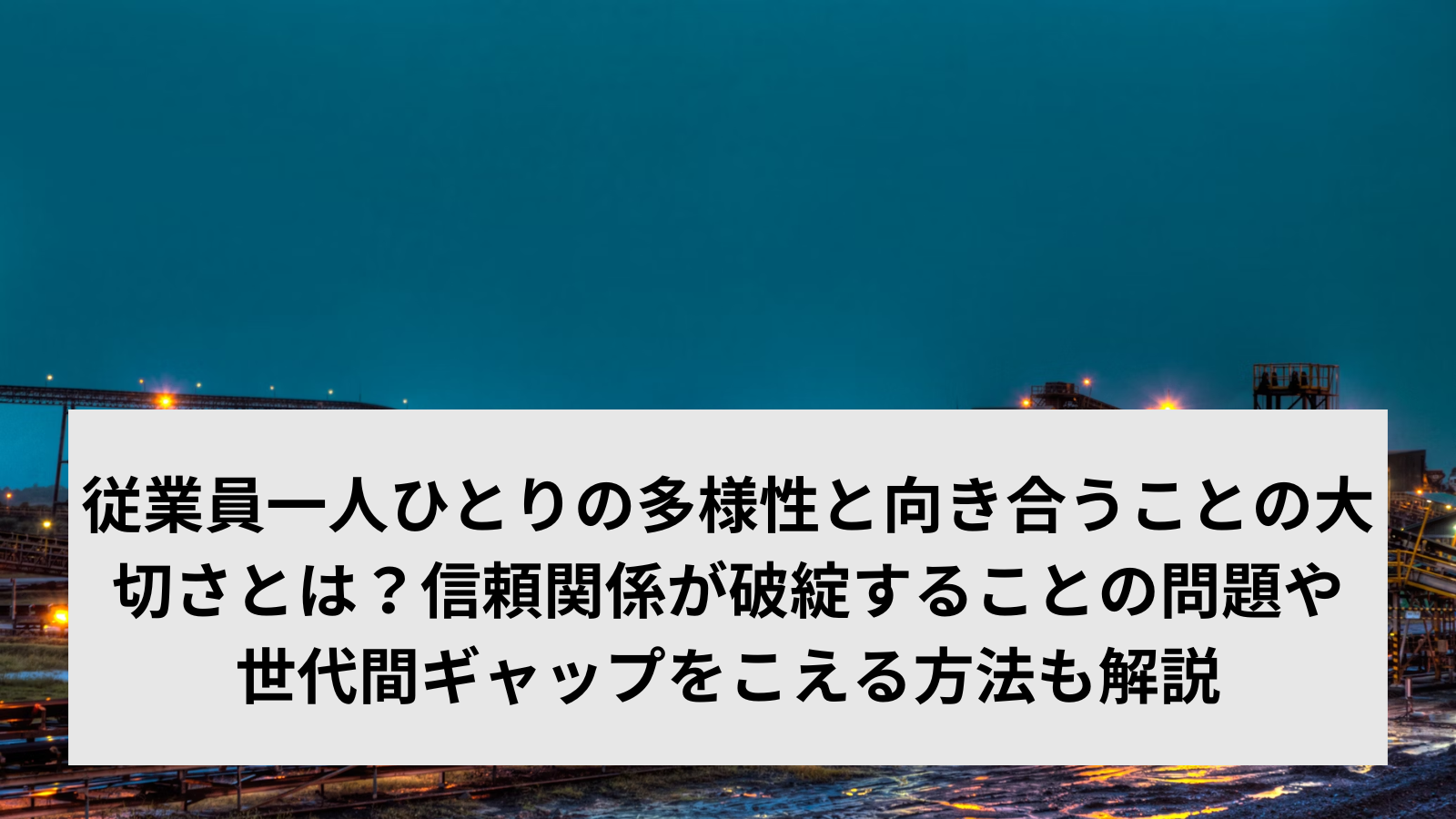OJT
アナログ作業が「考える力」を養う!取り組み方や事例を解説

監修者
三尾 恭生
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて42年の現場経験、管理職の経験を経てOJTソリューションズに入社しました。座右の銘は「不易流行」。変える勇気と変えない勇気を持つことが大事だと信じ、現地現物でお客様と伴走しています。
製造現場のDX化はトヨタにおいても例外ではありません。帳票のペーパーレス化などの基礎的なものはもちろん、外観検査工程でのAI活用など多岐にわたります。最近では、紙やホワイトボードで運用をしていた日常管理板や生産管理板の電子化も大きく進んでいます。
このようなデジタル化を進める一方で、従来からの「手を使う」アナログな部分も残しています。効率やデータの保存という観点ではデジタルに軍配が上がるでしょう。しかし手書きにもメリットがあります。手を使って考えることで、思考力や当事者意識が高まる場合もあります。
参考記事:トヨタの日常管理とは?進め方や日常管理板を使う3つのメリットも紹介
本記事では「考える力」を養う、という視点からアナログ作業のメリットや取り組み方について解説します。
手で書き入れることに意味がある
多くの製造現場で取り入れられている「生産管理板」を例にご紹介します。生産管理板とは、「今日1日で何個生産する」目標があるとしたら、1時間ごとに目標の生産数を設定し、その通りに生産できているかをチェックし、生産の結果を書き入れる(入力する)ものです。こうした「毎時間ごとに数値を記録する」行為は、生産を守るために重要な役割を果たします。
担当者が実際に生産数を目視で確認し、生産管理板に書き込む(入力する)ということは、「その担当者の責任で生産が管理されている」ということです。担当者が毎時間記録するプロセスがあることで、現場の正常・異常に常に注意を払い、生産数が達成できなかったときにはすぐ原因を考え、設備の様子を見回るなどの対策を実施できます。
トヨタも生産管理板のしくみを取り入れています。工場ごとに差はありますが、時間あたりの生産数をホワイトボードに書き入れる作業をいまだに続けています。もちろん、設備には生産数をカウントする機能が備わっており、ホワイトボードがなくとも生産実績を把握することは可能です。ではなぜホワイトボードの記入を続けているのでしょうか?
ひとつは当事者意識の醸成です。生産しているメンバー自身が結果を「書く」行為が当事者意識を生むと考えているからです。米国プリンストン大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究によると、手書きはキーボード入力と比較して記憶の定着が強いそうです。皆さんも感覚的になんとなく理解できるのではないでしょうか。書く行為で生産の実感を強め、当事者意識を高める。これがひとつめの理由です。
また、手作業で生産管理板に記入していると、生産数変化の原因に気付く目が養われます。例えば、9時から10時は「現場にはじめて入った新人に説明するため、少々遅れが発生した」、10時から11時は「急激に生産数が下がった。すぐに調べてみると、ある箇所が少し動作不良を起こしていた」などと把握できます。システムを使い自動で生産進捗管理をしている場合でも、1時間ごとに進捗チェックをする習慣があれば同じように変化に気づけるかもしれません。ただ、多くの場合このようなチェックの作業は形骸化していきます。一見ムダに思える「時間ごとに結果を書く(入力する)」行為が問題に気付く目を養います。
一概に生産管理板は手書きの方が優れている、手書きにすべきだ、ということではありません。トヨタでも工場やラインによっては手書きを廃止しているところもあります。現場の当事者意識や考える力にお悩みの場合、短期間でも手書きを取り入れてみると何かいい変化を感じられるかもしれません。
まずは手書きで考えてみる
続いては日常管理板を例にご説明します。日常管理板とは、月次の指標や日次の指標、日々に実践した問題解決を視える化する掲示板のようなものです。現在のトヨタでは、ほぼすべてがデジタルモニターになっています。数値データをグラフに表しますが、このグラフに表す過程、グラフを考える過程に手書きのメリットがあります。
トヨタの日常管理板では、「現状をわかりやすく示すグラフにするには、どう表現したらよいか」を現場のメンバー全員で考えることを大切にしています。アイデア時点ではよいと思っても、必ずしも分かり易いグラフになるとは限らず、形になるまで試行錯誤がともないます。
システムやソフトでの管理一辺倒にすると、はじめはみんなで考えても、最終的に扱いに慣れた人任せになってしまいがちです。そのため「どんな見せ方にしたいか」「どんなグラフならわかりやすいか」を考える過程では手書きを活用します。そこで決まった見せ方を、デジタルに落とし込みます。
2020年頃までトヨタの日常管理板はほとんど手書きでした。手書きの時代に磨かれた「見せ方」が今のデジタルに落とし込まれているため、今でも現場の皆が見やすく、納得できるグラフが表現されています。
まとめ
本記事ではデジタル時代にあえて「手を使う」というトヨタの事例を紹介してきました。手書きには、当事者意識や考える力を高める効果があります。
最近はトヨタでもDX化が大きく進んでいます。トヨタも過渡期にあり、デジタルの良さと手書きの良さを両立する方法を模索しています。たとえば一度デジタル化した帳票を、現場の声を受けていったん紙に戻す、ということもおきているようです。世代間ギャップも起きやすいテーマです。目的に応じて、あえて手書きを選択する場面があってもいいのではないでしょうか。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
アナログ作業が「考える力」を養う!取り組み方や事例を解説
2025.04.18 -
部下との相互理解が深まる「基本心得」4選
2025.03.14 -
トヨタ式のメンバーの叱り方!リーダー同士の役割分担や想いを伝えることの重要性も紹介
2025.01.17 -
ひとくせある部下から育てるのはなぜ?部下に理解・納得させる重要性も解説
2024.10.25 -
2つ上の目線でリーダーを育てる重要性とは?トヨタの研修の仕組みを紹介
2024.10.18

PAGE
TOP