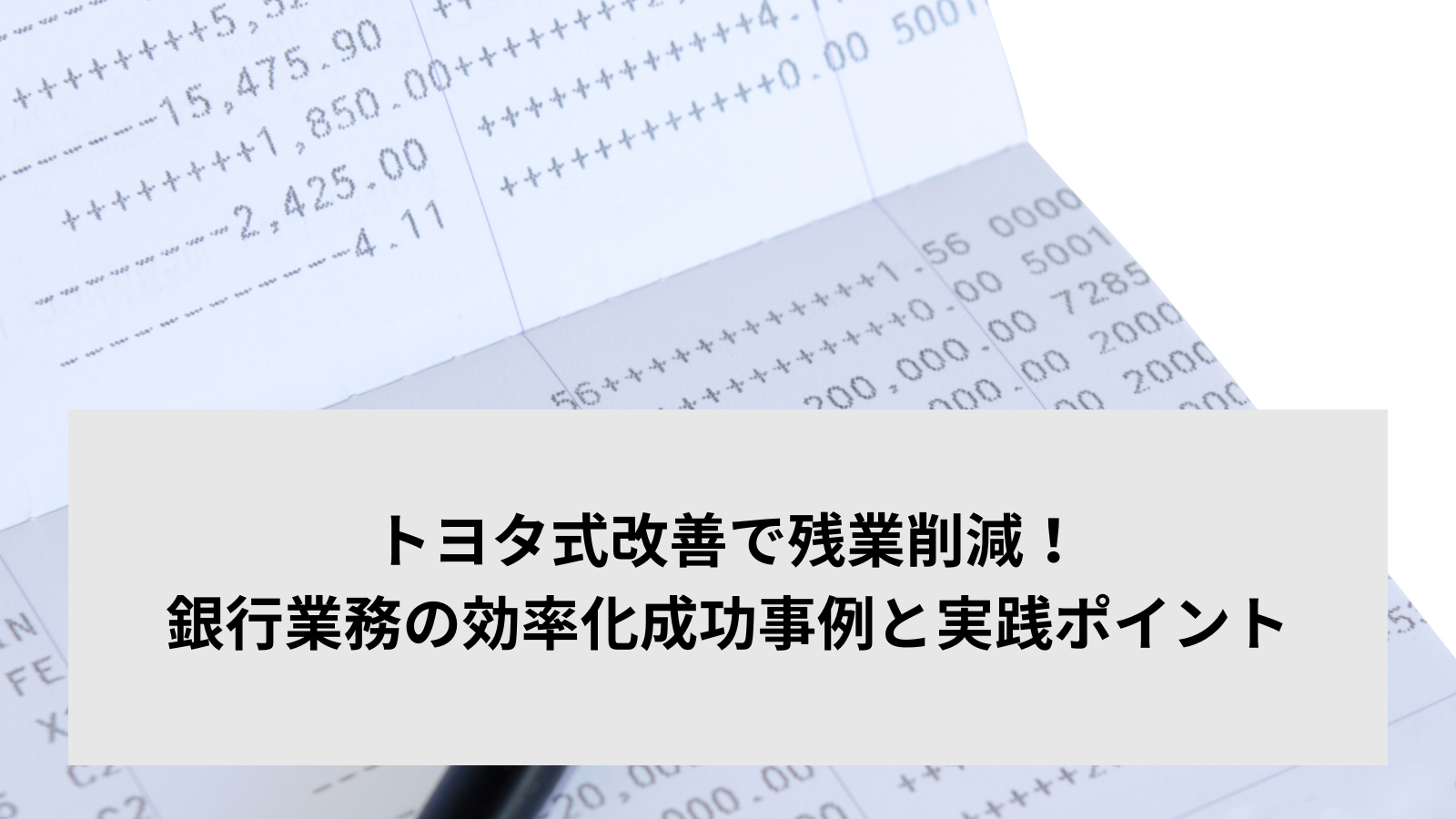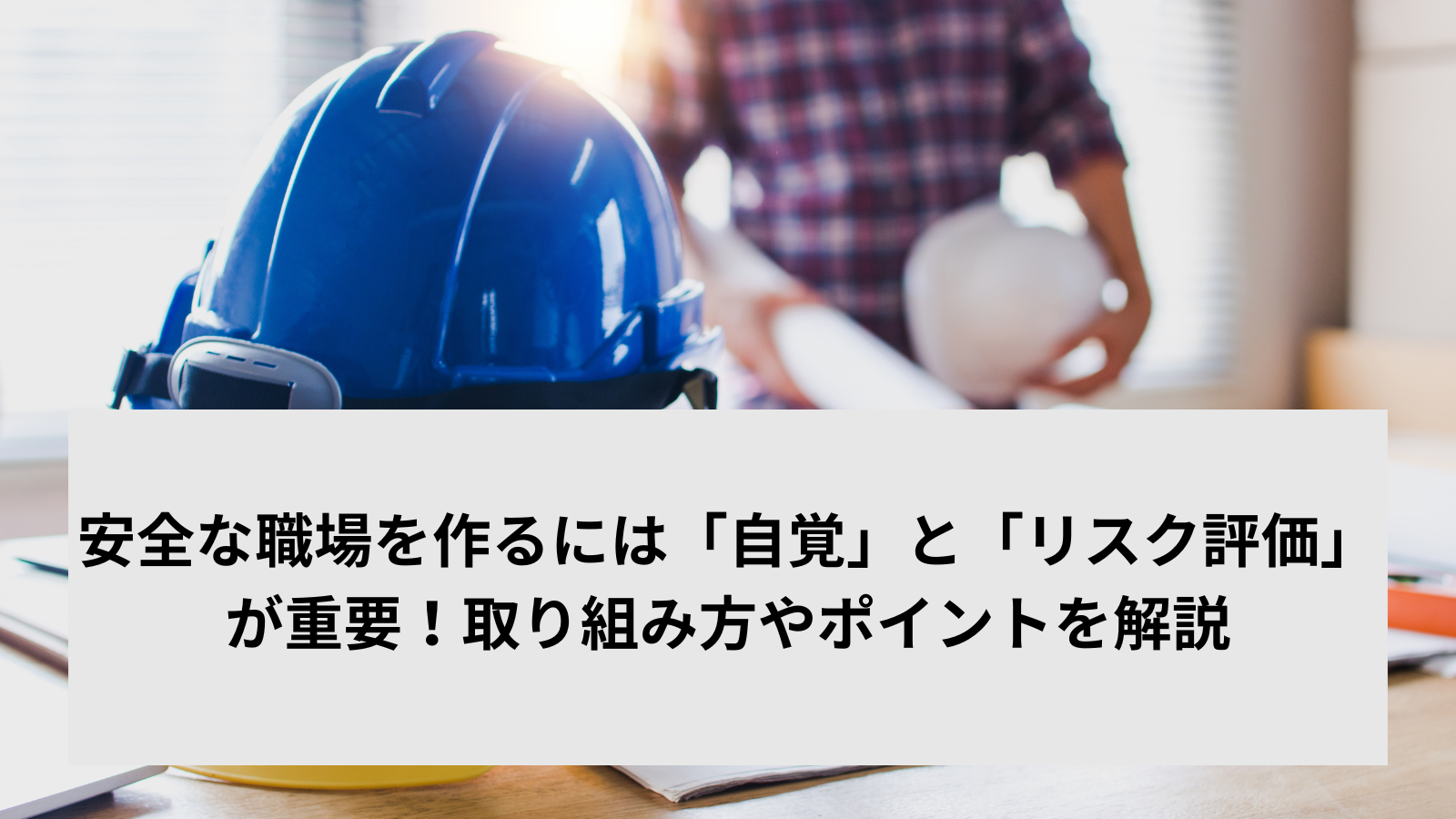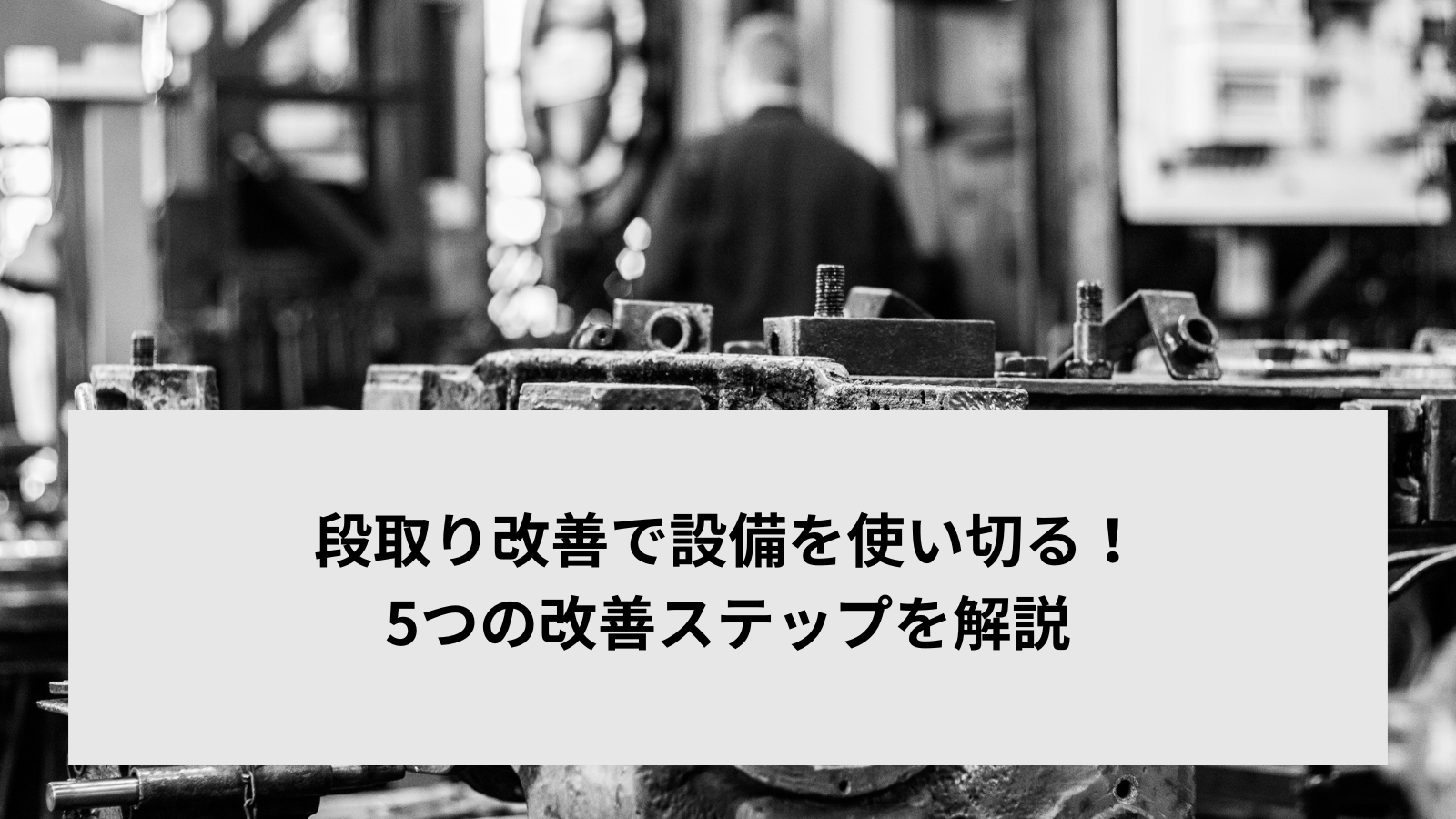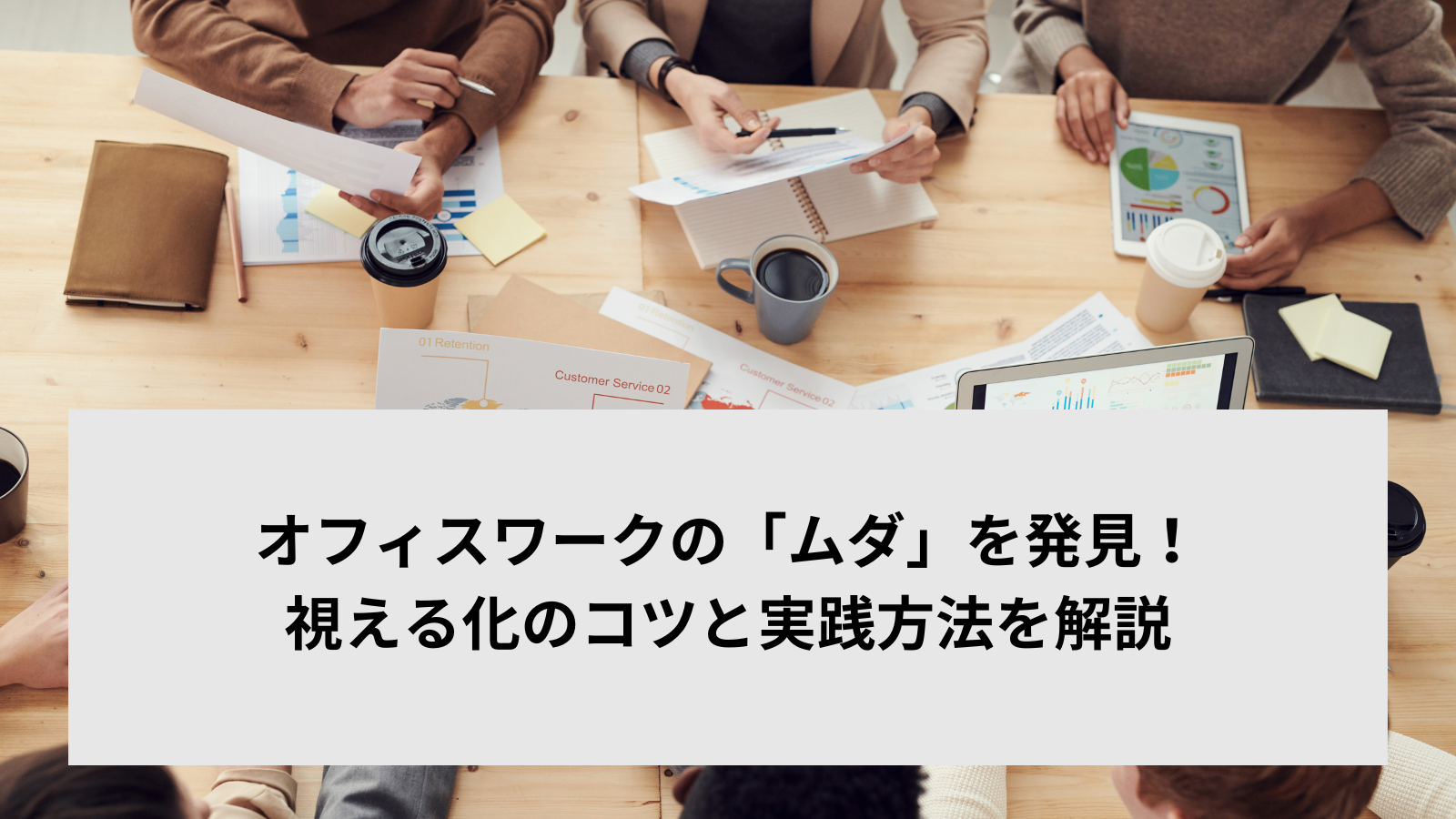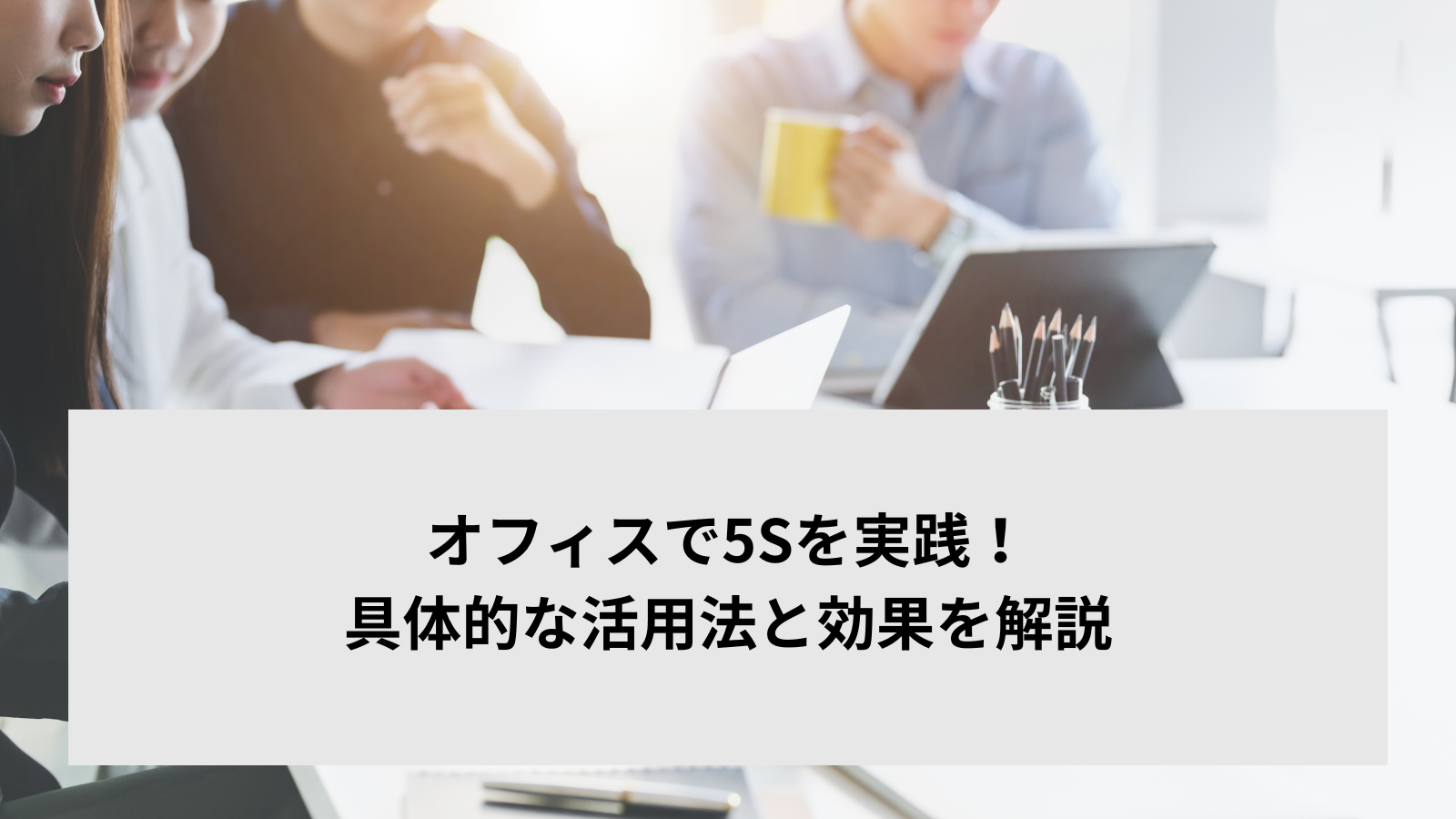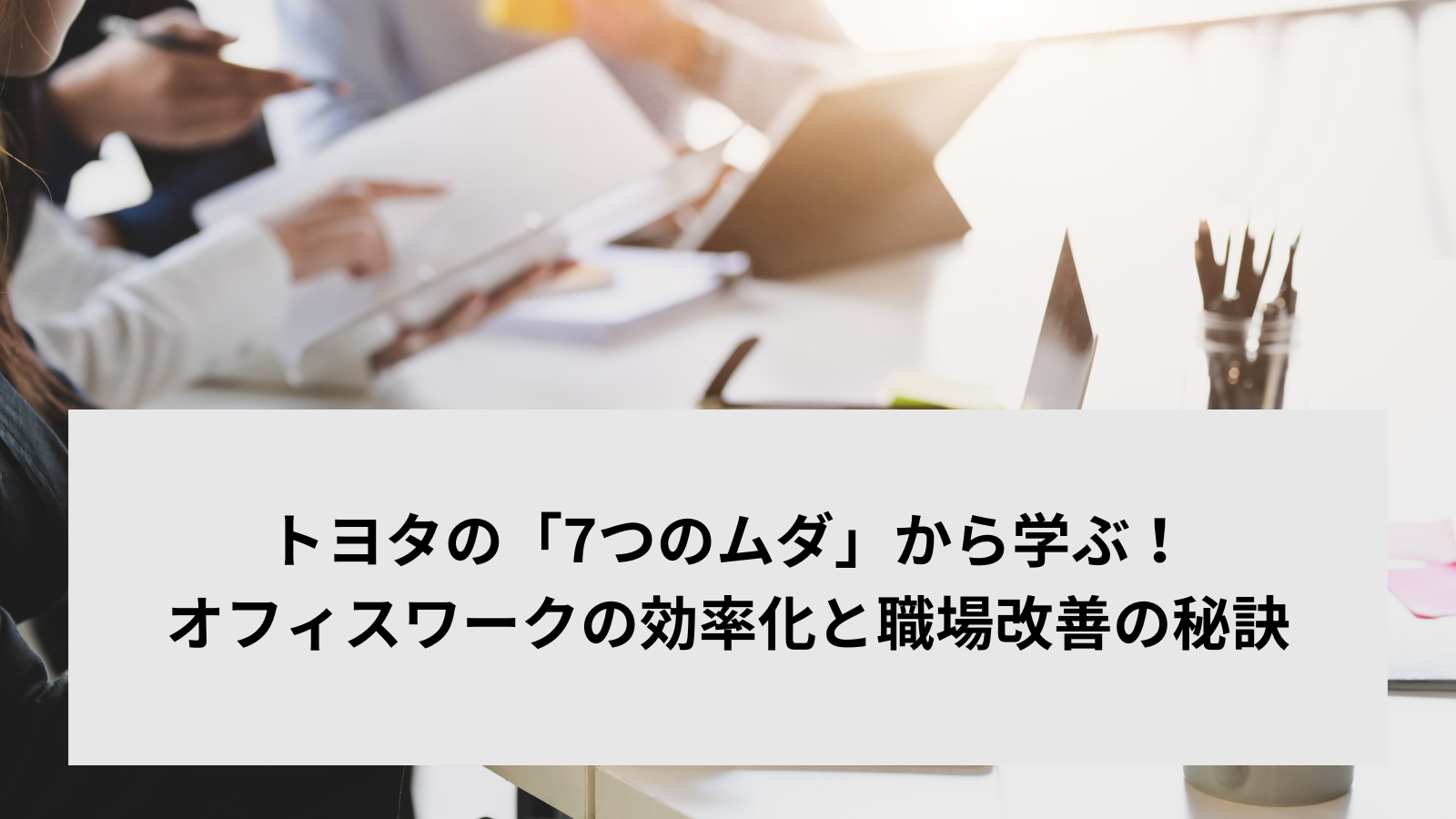現場力向上
トヨタ式改善で残業削減!銀行業務の効率化成功事例と実践ポイント
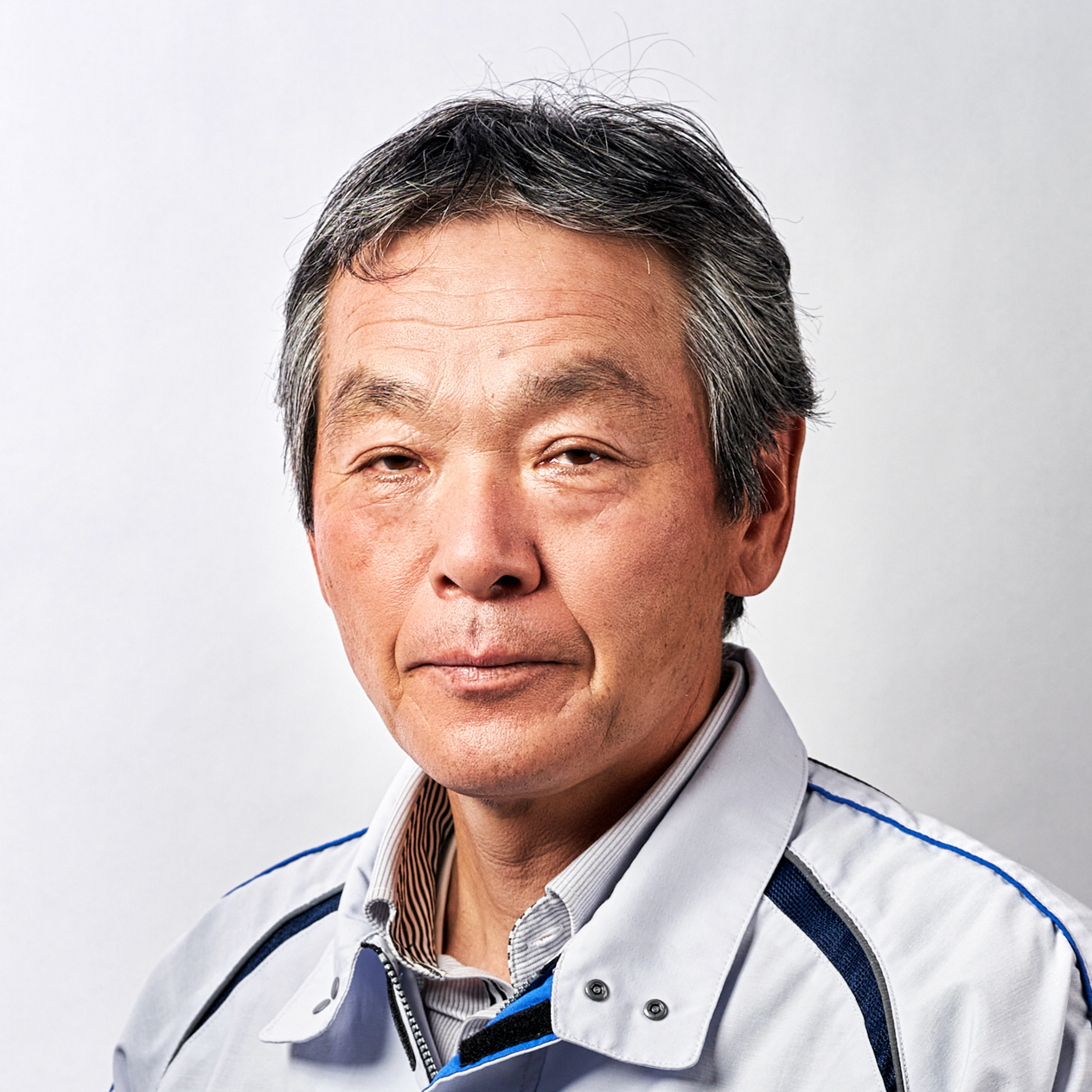
監修者
山本 昭則
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車のプレスにて39年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。改善活動には時に大変な場面もあります。それを乗り越える笑顔、会話を特に大事にしています。休日は趣味の山小屋づくりで精神統一をし、日々の仕事の英気を養っています。
非製造業の職場で「業務効率を上げたい」「残業を減らしたい」「サービス品質を向上させたいが、何をどう改善すればいいかわからない」というお悩みをよく耳にします。
オフィスワークでは目に見えないものを扱うことが多いため、課題や問題がわかりにくく、改善の糸口がつかみにくいと感じる方も多いでしょう。
しかしトヨタ式改善の考え方は業種を問わず応用可能です。本記事では、銀行での残業削減事例を通して、その具体的な手法をご紹介します。
ある銀行の課題
この銀行では、「残業が多い」という問題が顕在化していました。しかし、実態としては純粋に業務量が多く「帰れない」人、業務は終わっているが「空気を読んで帰らない」人がおり、結果的に全員が残業をしているという状況でした。
現状調査と分析
まずは改善メンバーと現状調査に取り組みました。具体的には、窓口担当を中心に、1日の仕事をすべてビデオ撮影し、さらに個人にそれぞれやったことのリストを時間別に書き出してもらいました。
解析の結果、「窓口が閉じたあとの業務」に時間がかかっていることが判明しました。トヨタの言葉を使えば業務の中に「ムダ」がある状態でしたが、本人たちにはまだ「ムダ」という意識がなく、その業務にも真面目に取り組んでいました。
「ムダをムダと気付けない」状態であったため、業務を「窓口業務」「日締め業務」「日締め以降業務」の3つに分解し、それぞれにかけている時間を数値化しました。
数値化したデータをもとに優先順位を決め、ここではステップ①日締め業務、ステップ②日締め以降業務、ステップ③窓口業務の順で改善を進めました。
改善の優先順位付けをするために、「現状分析」はとても重要です。数値で表すことを意識するとよいでしょう。
3つのステップによる改善プロセス
ステップ①:日締め業務の改善(自工程完結)
ステップ①では「自工程完結」に取り組みました。
トヨタの「自工程完結」とは、自分の工程(作業)に責任を持ち、後ろに不良を流さない、という考え方のことです。
この銀行では現金事故や間違いを防ぐために、窓口業務者以外で3重のチェックをしていました。この場合の工程は大きく分けて3工程です。窓口の人が記入書類を目視確認し、後方担当者が再度の確認、役席が3度目の確認をし処理をする、というやり方でした。
ここでは、窓口の人の確認方法を改善しました。目視のみだったところを、帳票チェックのやり方のルールをつくり、それを徹底しました。
ここで重要なのは、やり方の話ではなく、作業者の意識です。以前は「後ろの人がミスに気付いてくれるだろう」という思いで作業をしていましたが、自分たちでルールを作り自工程完結するという意識が芽生えたことで、結果的にミスの削減とともにやり直しの処理が減り、時間を短縮できました。
ステップ②:日締め以降業務の改善(当たり前を疑う)
ステップ②では、「日締め以降業務は窓口が閉まってからしかできない」という当たり前を崩すところから始めました。
ここでやったことは、すごく単純です。夕方に1回にまとめておこなっていた業務、入出金や税金処理を、午前と午後の2回に分けておこなうようにしました。
これを聞いて「なんだそんなことか」と思うかもしれませんが、昔からやっていてこれが当たり前、という作業の課題にはなかなか気付くことができません。トヨタに伝わる格言で「問題を問題と思えないのが一番の問題だ」というものがあります。
自社の「当たり前」を疑うことが、問題解決を進める鍵になります。
ステップ③:窓口業務の改善(繁閑差対応と手待ち削減)
ステップ③では、取り組んだのは2つ、繁閑差に応じた人員配置と、手待ち、つまり「窓口が何もしていない時間」の短縮です。
まず時間に分けてお客様の数を計測し、時間ごとに必要な窓口数を決めました。お客様が多い時間帯はフルで窓口を開け、少ない時間帯は窓口を少なくし、空いた人間は後方の処理にまわることで、業務を効率化しました。
さらに、お客様の動きにも注目しました。従来は「受付表を取ってから書類記入する」やり方で、お客様にも窓口担当にも待ちが生じていました。これを「書類を記入してから受付表をとる」というやり方に変更し、この順番でスムーズに流れるように店舗のレイアウトも変更しました。その結果、窓口担当の時間あたりの処理能力が上がり、お客様の待ち時間も減少しました。
結果と成功要因
これら3つのステップによる取り組みで、一人月あたり約20時間の残業削減に成功しました。
成功要因をまとめると下記の3つになります。
- 現状分析による課題の視える化(数値化)
- 優先順位付けによる段階的アプローチ
- 「当たり前」を疑う視点と地道な取り組み
この支店の取り組みは全社表彰され、頭取からも直接評価されました。活動メンバーにも大きな達成感が生まれました。
まとめ
今回ご紹介したように、非製造業でもトヨタ式改善手法は有効です。以下のポイントを押さえて実践してみてください。
- 現状把握: 数字で作業内容や時間配分を可視化する。
- 優先順位付け: 数値データに基づき、重要度・緊急度で判断する。
- 段階的実施: 一度にすべて解決しようとせず、一つずつ着実に進める。
- 問題意識醸成: まずはやってみて、活動の中で問題意識を高める。
問題解決、改善を進めることは容易ではないですが、ご紹介した事例をぜひ改善活動のヒントにしてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28 -
トヨタ式改善で残業削減!銀行業務の効率化成功事例と実践ポイント
2025.03.28 -
オフィスで5Sを実践!具体的な活用法と効果を解説
2025.03.21 -
トヨタの「7つのムダ」から学ぶ!オフィスワークの効率化と職場改善の秘訣
2025.03.21

PAGE
TOP