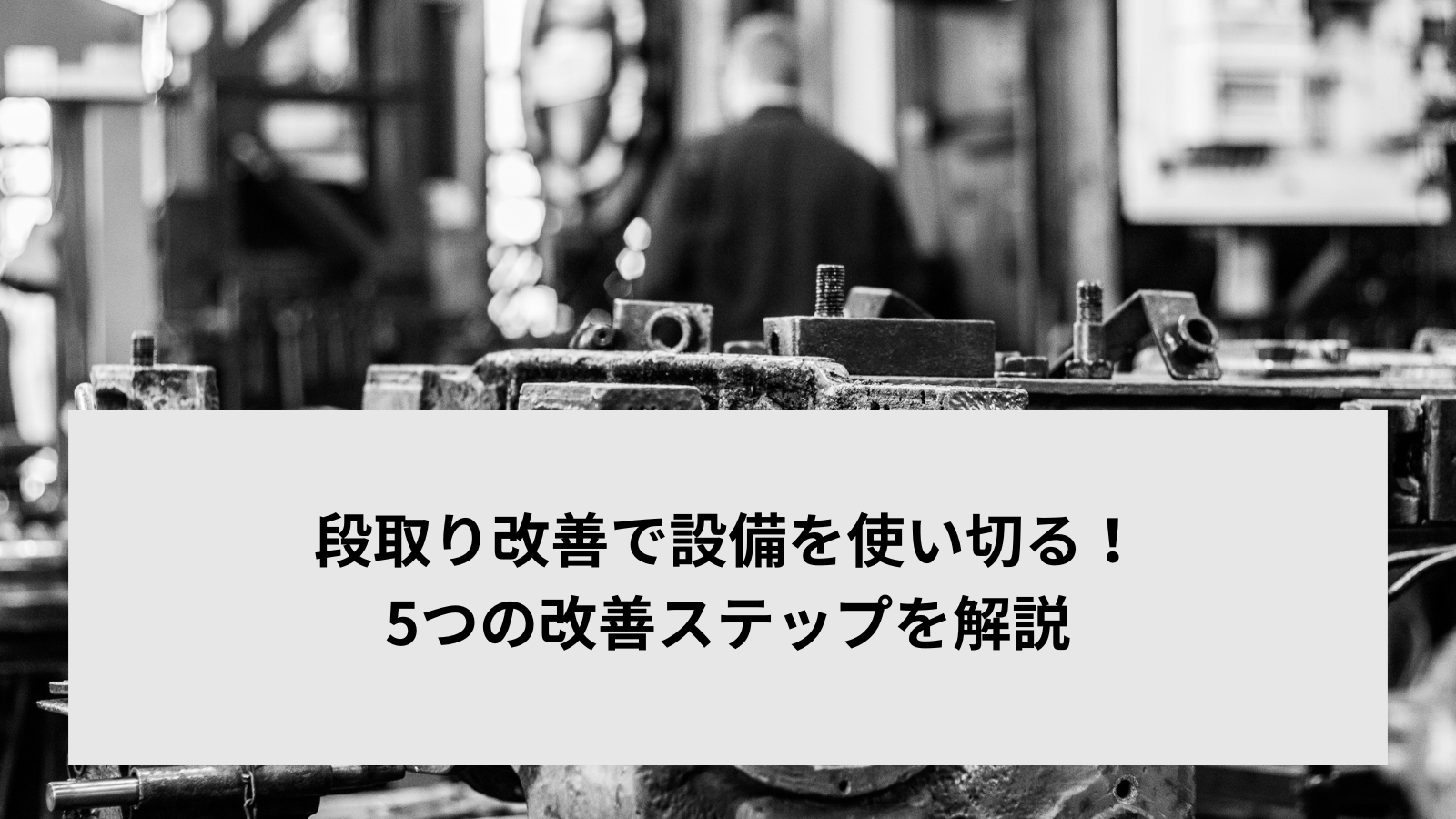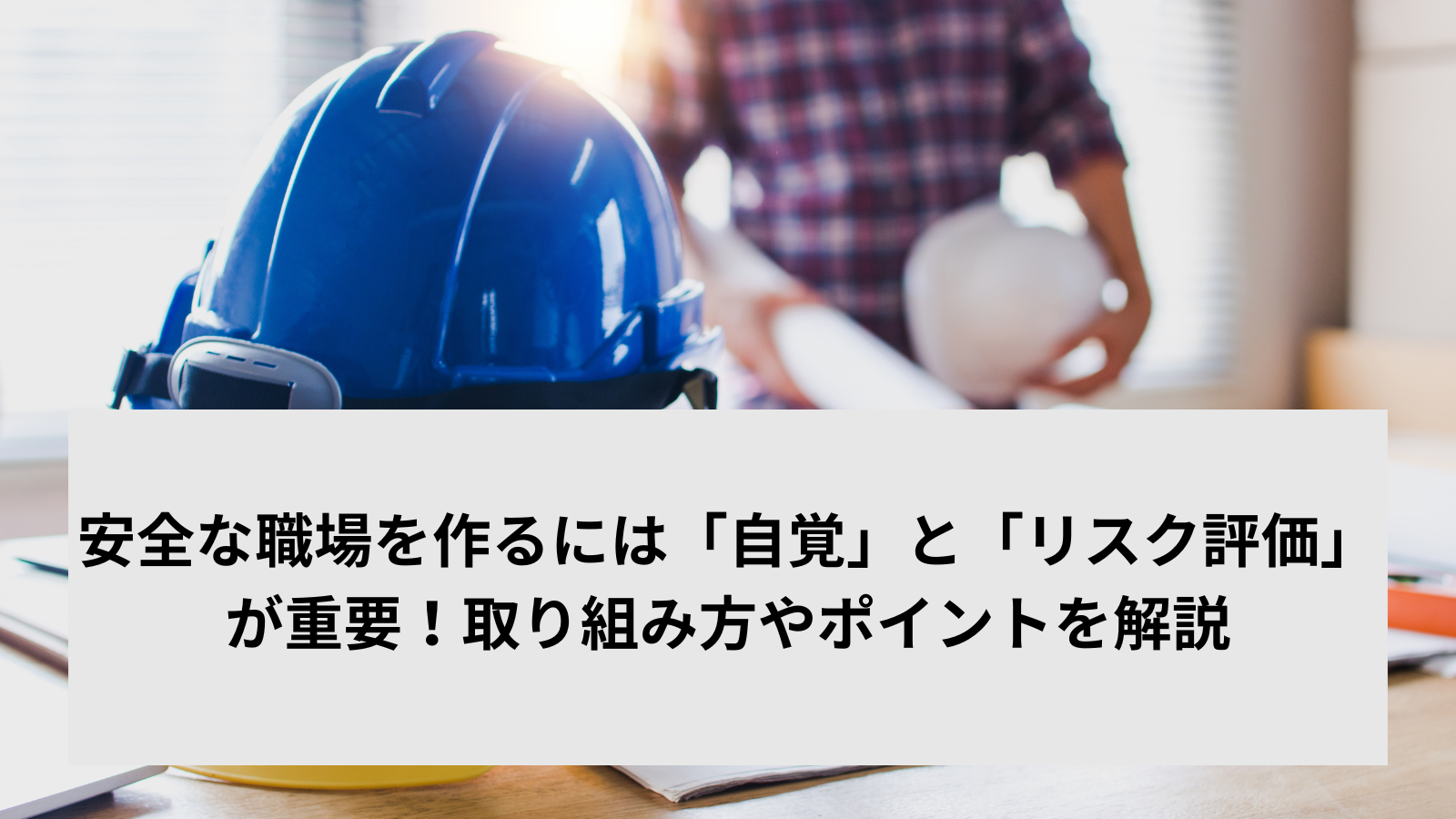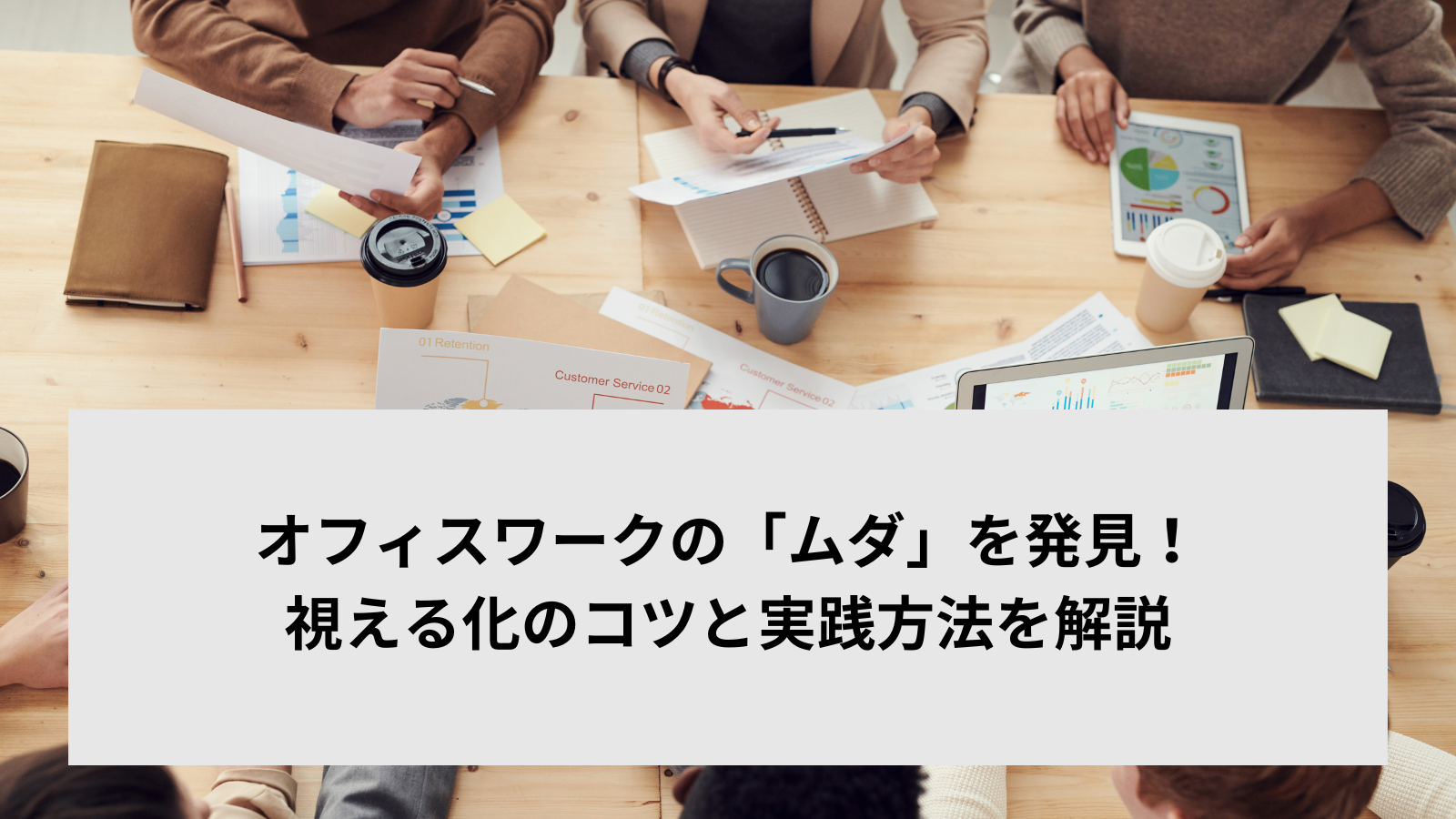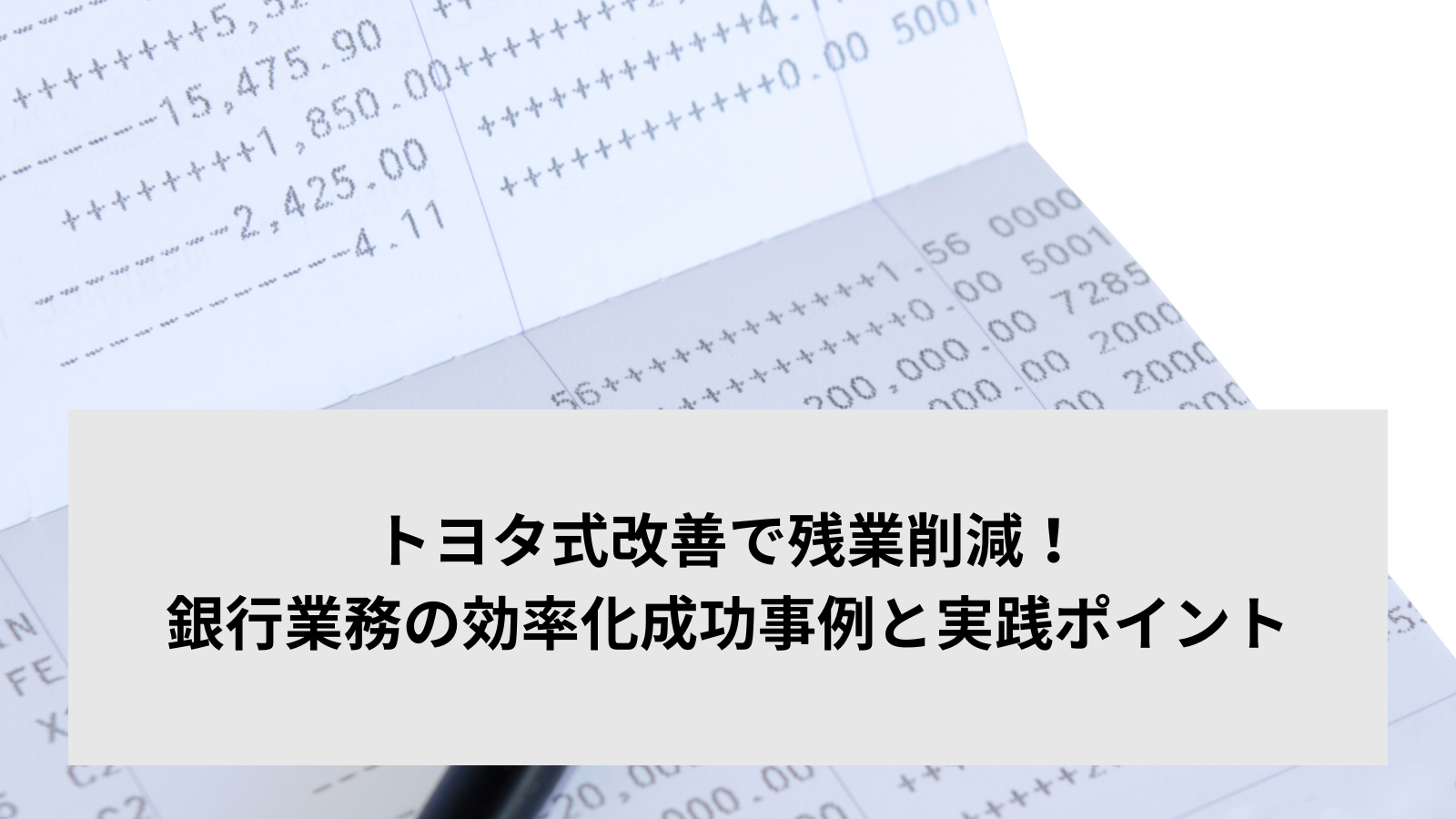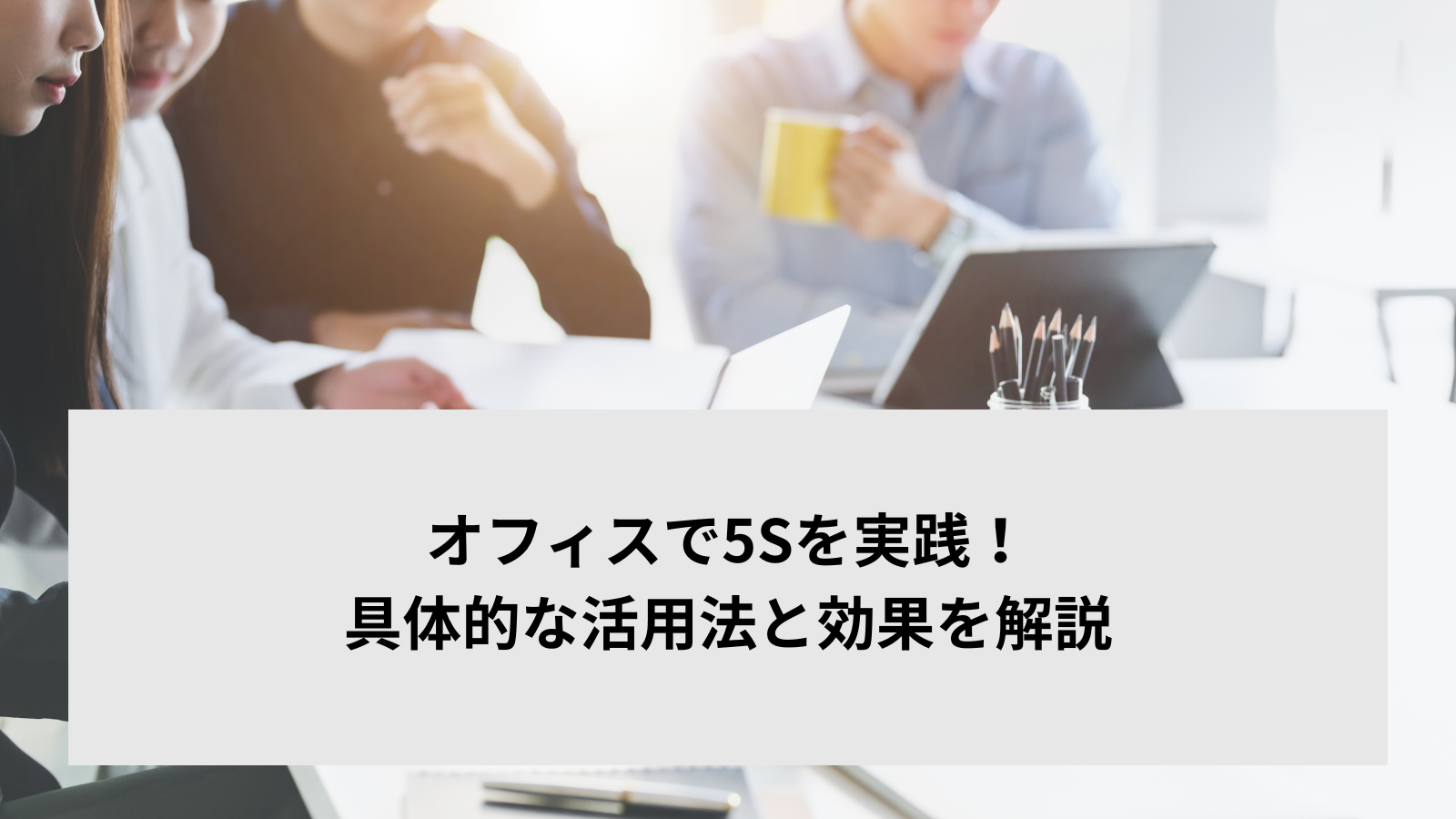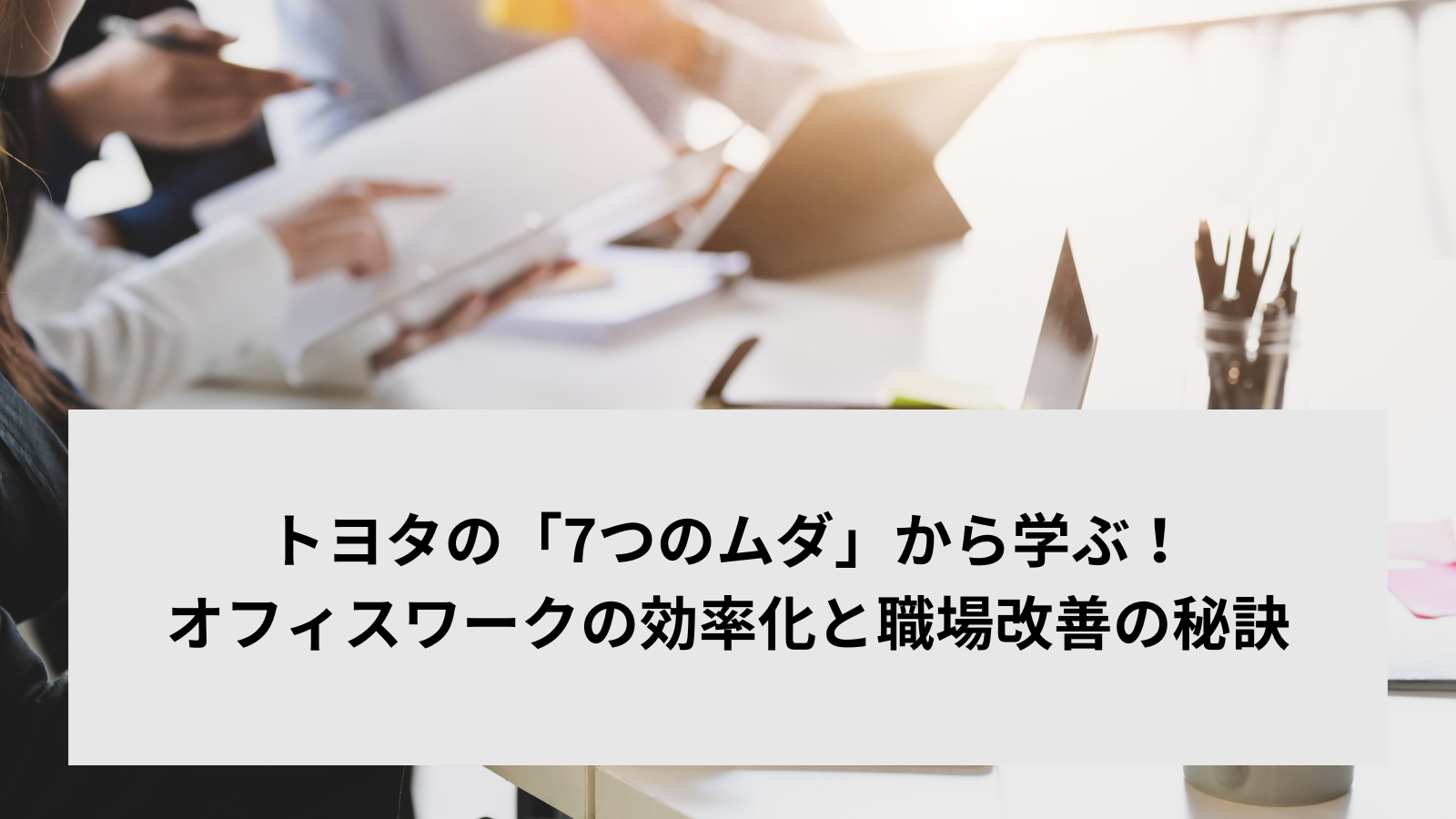現場力向上
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
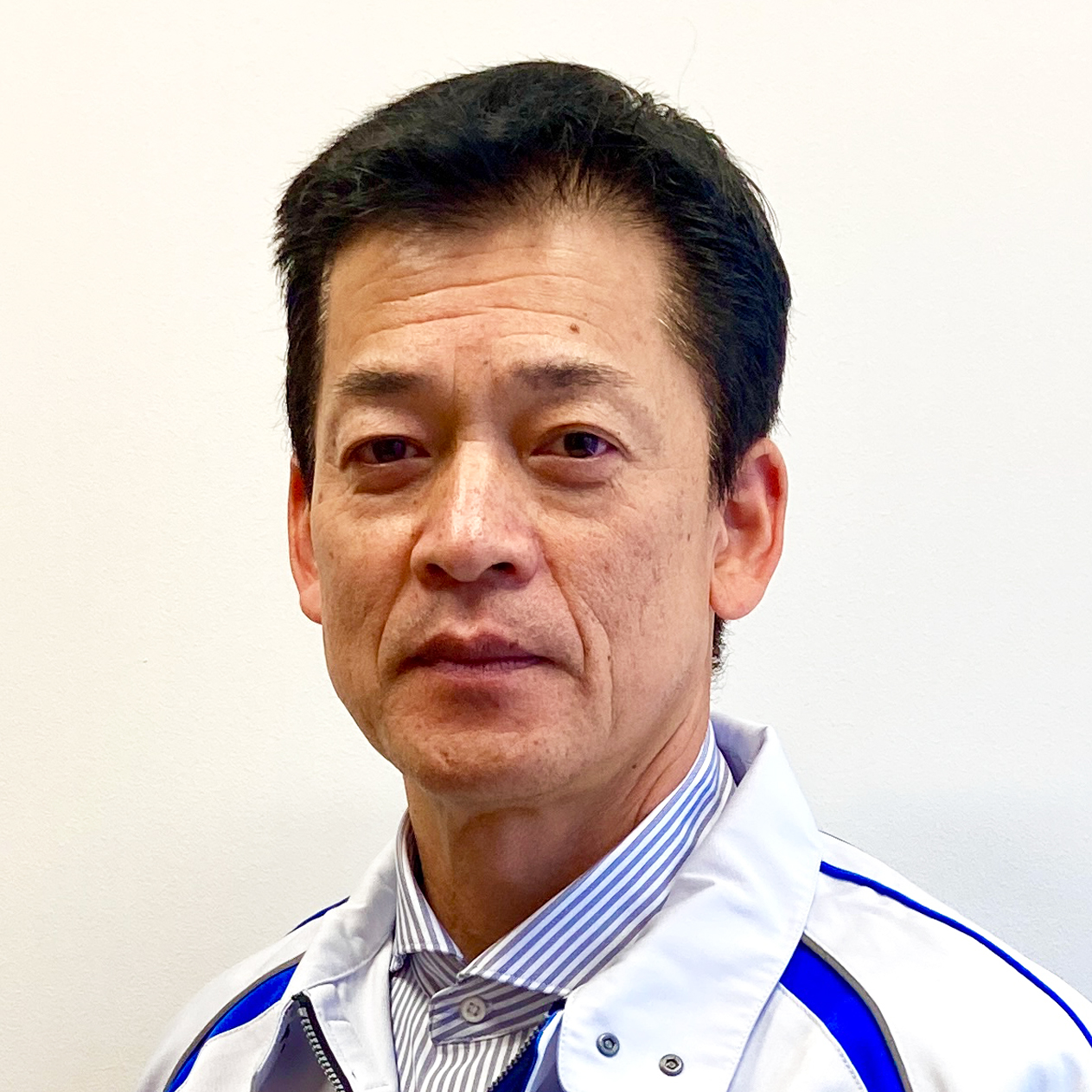
監修者
文室 義広
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて、製造現場の改善、販売店の事務系改善などの42年の経験をへてOJTソリューションズに入社しました。少林寺拳法で鍛えた「自他共楽」の精神を胸に、お客様の会社の社員になった気持ちで日々改善活動に伴走しています。
最近の製造業では市場のニーズの多様化による影響として、多品種少量生産や生産リードタイムの短縮、短納期化が求められている、という課題をよく聞きます。競合他社に対する優位性を維持するためにも、これらの課題を解決し効率的な生産を実現することが必要です。
このように、限りある時間のなかで多品種少量生産に対応し、効率的な生産を実現するためには、段取り時間の短縮が有効な改善手段となります。本記事では段取りを改善する手法について、トヨタの「人と設備が持っている能力を最大限に活用する」という視点から解説します。
段取りとは
「段取り」とは、物事をおこなう際の順序や手順、準備のことを指します。製造現場においては、ある製品から別の製品に生産を切り替える際に発生する準備などが「段取り」にあたります。
ものづくりをおこなううえで重要な作業の一つですが、段取り作業は付加価値を生みません。そのため、段取り作業時間を短縮し、付加価値を生む作業時間をより多く確保することが設備稼働率の向上や生産の効率化につながります。
段取り時間短縮の5つのステップ
段取り時間の短縮は、5つのステップで進めます。
- 段取りを3つに分解
- 内段取りの外段取り化
- 内段取り時間の短縮
- 調整時間の短縮
- 外段取り時間の短縮
それぞれ解説します。
①段取りを3つに分解
まずステップ①では、現状の段取り作業を細かく分解し、「内段取り」「外段取り」「調整作業」の3つに分けていきます。
内段取りは、設備を停止させなければできない作業、つまり前の生産が終わらないとできない作業のことです。
外段取りは、設備の稼働中に、設備外で次の製品を生産するための事前にできる作業のことです。
調整作業は、内段取りが終了したあと、規格にあった良品をつくるために設備等のさまざまな調整をおこなう作業のことです。
②内段取りの外段取り化
次のステップ②では内段取りでおこなっている作業のうち、設備が停止した後でなくてもできる作業を外段取り化します。
普段、当たり前に内段取りとして扱っている作業も、改善意識をもって現場を視ることで外段取り化できることに気づけるかもしれません。外段取り化できる作業をすべて移行することで、内段取り時間の短縮、つまり設備が停止している時間を短縮できます。
③内段取り時間の短縮
次のステップ③では、どうしても設備停止後でないとできない内段取り作業時間の短縮をおこないます。残った内段取り作業をよく観察し、細かな分析を通じて、作業からあらゆるムダを徹底的に排除し、効率化を進めます。
具体的には、作業方法の改善や段取りに使用する治工具の作成・改良などの改善があげられます。例えば作業方法の改善では、一人が連続でおこなっていた複数の作業を、複数の人が並行して作業する方法を探るなど、あらゆる面で設備の停止時間を短縮する方法を検討し、実施します。
④調整時間の短縮
ステップ④では、規格どおりの製品をつくるための調整時間の短縮をおこないます。品質が保証された製品を生産するための調整作業は欠かせませんが、設備を止める必要があるため長い時間はかけられません。
まずは、作業のなかで不必要な調整があるかどうか確認し、あれば即座に廃止します。
また、経験やカンなどにより人が判断しなければならない作業を、いかに「調節」にするかも重要です。「調節」とは、自動化や測定の数値化、設備や治工具の精度アップなどにより機械的にできるようにすることです。「調節」によって作業が正確で容易となり、時間を短縮できます。
このステップ④までで、内段取りと調整による設備停止時間をできる限り短縮します。
⑤外段取り時間の短縮
最後のステップ⑤は外段取り時間の短縮をおこないます。外段取り時間は設備停止時間に影響はありませんが、段取りの総工数を減らし、総合的な効率向上の観点からも、大切な改善です。
外段取り改善のポイントは3つあります。
1つ目はモノを探すことの排除です。これは、5Sの整理と整頓を実施するだけでも、モノを探す時間は大きく低減できます。
2つ目は運搬の排除です。よく使うものは近くに置くことでムダな運搬をなくすことができます。
3つ目は、作業標準書を作成し、作業手順を明確化することです。段取りに使用するものを集める手順が最短になるように作成することがポイントです。
また、このように効率化した段取りの作業手順や方法を標準化することも重要です。ルールの明確化によって、誰でも同じ時間で、間違えのない段取り作業が実現できます。
段取り改善の成功事例
段取り改善を成功させるポイントは、現状の作業を細かく観察、分析し、人の知恵を使って一つずつステップを踏んで進めていくことです。そのために、まずは今ある設備と作業内容を現場が十分に把握することが必要です。
ある電子部品メーカーでの段取り改善事例をご紹介します。この企業では「高品位な商品を、より早く・より安くお届けする」というお客様の要望にお応えし、競合他社に圧倒的な差をつけた納期を実現するために、生産性向上と、生産リードタイムの短縮が急務の課題でした。
現場では多品種少量のロット生産に対応するために、どの工程も一日あたり数回の段取り作業が必要でしたが、ある工程では設備稼働率が47%と、1日の稼働時間の半分にも満たない状態でした。
設備稼働率を阻害する最も大きな要因は、段取り替え作業時間で設備停止時間の4割ほどを占めていたことでした。1日7時間のうち、段取り作業に1.5時間も費やしていたことになります。
そこで、この工程の段取り時間の短縮に向けた改善をおこなうことになりました。
まずステップ①の作業を3つに分解するところでは、ビデオ撮影した実際の作業を観察し、解析表などの分析ツールを使いながら、内段取り・外段取り・調整作業に分解してそれぞれの作業にかかる時間を明確に仕分けしました。
次のステップ②の内段取りの外段取り化では、これまで内段取りでおこなっている作業の中から、事前に準備できる作業4項目を外段取り化できました。
そしてステップ③の内段取り作業時間の短縮では、作業者の動作観察、歩行の観察から、主に動作のムダ、運搬のムダを見つけ出し、複数の作業改善を実施することで時間短縮につなげることができました。
続いてのステップ④の調整時間の短縮では、改善メンバーの知恵によって大きな改善が実現できました。製品にインキを塗る工程で使用する印刷用の版は、段取り替え時に弛みの補正が必要で、熟練者でも時間がかかる作業です。これを何とかしたいと弛みの要因を追究したところ、使用後の洗浄・乾燥工程で発生することがわかったため、事前に弛みを補正する改善を行いました。その結果、補正作業の外段取り化が実現し、設備停止時間の大幅な低減を実現しました。
ステップ⑤の外段取り時間の低減でも、部品の運搬経路などの改善をおこない、効果として段取りによる設備の停止時間は日あたり1.5時間から45分程度になり、約50%低減できました。
まとめ
多品種・少量化、リードタイム短縮の実現に有効な、段取り改善の5ステップを紹介しました。
- 段取りを3つに分解
- 内段取りの外段取り化
- 内段取り時間の短縮
- 調整時間の短縮
- 外段取り時間の短縮
段取り改善を成功させるためには、現状の作業を細かく観察、分析しながら、ステップを踏んで進めていくことがポイントになります。そのために、まずは今ある設備と作業内容を現場で十分に把握することが必要でしょう。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28 -
トヨタ式改善で残業削減!銀行業務の効率化成功事例と実践ポイント
2025.03.28 -
オフィスで5Sを実践!具体的な活用法と効果を解説
2025.03.21 -
トヨタの「7つのムダ」から学ぶ!オフィスワークの効率化と職場改善の秘訣
2025.03.21

PAGE
TOP